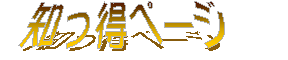|
知っ得情報
 ついに発見!カワイ楽器のメタル・クラリネット ついに発見!カワイ楽器のメタル・クラリネット
メタルクラリネットはマーチング用に1950年頃まで製作されていたものですが、メタルクラリネット協会 のホームページにメタルクラリネットをカワイ楽器が今でも発売しているらしい、という記事が載っていたのでカタログを調べたらありました。型番KCL−510S
B♭ 管体イエローブラス、キーシルバーメッキとしか記載されていませんでしたが、写真からは管体もシルバーメッキが施されていると思われます。2001年の価格は175,000円です。PIPERS20039月号「知りたい楽器!Metal Clarinet」の記事によると、この楽器はイタリアのオルジー社製だということですが、未だに製造している所があるなんて驚きです。
 香取良彦&Jazz Orchestra Live Specialレポート 香取良彦&Jazz Orchestra Live Specialレポート
10月27日(火)Live Jazz Court TUC(東京・岩本町)に、〜声と楽団の共演〜と銘打ったライブを聞きに行きました。これは芸術文化振興基金助成事業の一つとして行われたものでJazz
Orchestraに弦楽四重奏、コーラス、ボーカルを加えた大編成の企画で大変、聞き応えがありました。曲目が語りによって結合された形で演奏され、間合いのない形式でしたので、連続して感動が伝わり盛り上がりました。
今回の企画を香取さんはプログラムの挨拶文で以下のように述べていますので、一部をご紹介します。”・・・今回はまた少しその声の可能性を広げて、さらに声の不思議に踏み込んでみたいと思いました。つまり、声が楽器と言葉との曖昧な位置にあることに加えて、語りがストーリーと韻の狭間にあるような設定、(歌)詞なのか話なのか分からないような語り口、というともすれば意味不明になりがちな構成です。私は文学者でも詩人などでもないので、そちらの方面の専門家から見れば稚拙な遊びにすぎないと見られるかも知れません。しかし、音楽家の聴く言葉や声は、明らかに文字やその意味から入る言葉とは大きく異なる見方を伴っています。本日の場合、楽団と歌声と語りが同時に曖昧模糊としたバランスで、しかもそれでいながらトータルに強い印象を伴って聴いて頂くことができれば成功、と申し上げておきたいと思います。・・・”
本当にこの言葉通りの演奏でしたし、奥村 晶(TP)さんや佐藤達哉(TS)など豪華メンバーのソロも大変すばらしかったので、CDなどでまた聞けることを楽しみにしたいと思いました。
 神奈川県伊勢原のビッグバンドJazz Workshop "Afri" 神奈川県伊勢原のビッグバンドJazz Workshop "Afri"
伊勢原市民文化会館の主催でジャズ・アンサンブル・ワークショップが10月18日(日)のコンサートを目指して、5月1日よりほぼ毎週の練習を開始します。指導はあの伊波さんです。メンバーは公募され、6月26日現在何とかメンバーが揃いました。バンド名は地元で親しみのある大山・阿夫利(あふり)神社から伊勢原・Jazz Workshop "Afri"と名付けられました。今後の活躍を祈りたいものです。
デビューコンサートはお陰さまで大成功のうちに終了しました。来ていただいた方々には御礼申し上げます。私はクラリネットで北村英治さんと共演できて、感激しました。大変気さくな方で、すばらしい演奏を披露してくれました。"Afri"の今後は自主活動として継続しますのでご声援ください。
 三重県"The Salts &Sugars"のコンサート・レポート 三重県"The Salts &Sugars"のコンサート・レポート
8月16日三重県津市・三重県総合文化センターで開催されました"The Salts &Sugars"さんのコンサートに行って来ました。全国ビッグバンド名鑑でお知り合いになり、同県出身の私が帰郷するついでに(と云えば申し訳ありませんが)コンサートを聞かせていただきました。
一番感じたのは皆さん芸達者でドラムの人がバリトンを吹いたり、後で聞くとfluteはもちろん、oboe・vibraphone・tuba・cello・conga・bongo・timbales・尺八等ができるということです。我がNFCのサックス陣もいろいろやりますが同じ木管の中ということでしかありませんから、レベルが違います。それをベースにブルースやコンボ、デキシーなども演奏され、とても楽しいコンサートで、会場満員のお客様から大いに拍手がありました。
最近は旅に出ることが多いので、スケジュールが合えばお伺いします。全国のビッグバンドの皆さん、呼んで下さい。レポートします。
 ウィントン・マルサリス・バンド・クリニック・レポート ウィントン・マルサリス・バンド・クリニック・レポート
7月21日に横浜みなとみらいホールにてバンド・クリニックがありましたので各バンドにウィントン・マルサリスや The Lincoln Center Jazz Orch.のメンバーがアドバイスしたことを掻い摘んでレポートします。
(1)シンバルが最高音、ベースが最低音であり、その二つがサンドイッチのパンのようにその他の音を包むんだ。(と云うことは中音域の人は常に二つの音を聞いていなければならないということでしょう)
(2)そして、その二つ(ドラムとベース)は常に会話してないといけない。
(3)ベースはアコースティックの方が良く、アンプを付けなくても充分聞こえるし、ダイナミックスが付け易い。(曲にもよると思うが、マスサリスはアコースティックが好きだからでしょう)
(4)リズムセクッションも一つ一つの音を大切に、ダイナミックスに注意しながら歌うように演奏しなさい。
(5)後方にいるTpもA.Saxの音を聞きなさい。(聞こえるように演奏しなさい)
実際のThe Lincoln Center Jazz Orch.は、とてもダイナミックスがあり(マスサリスも最も大きな音量の時は真っ赤な顔をして吹いていましたし、最低の音量の時はもう終わったんだと思って拍手が沸いた程小さな音量になっていました)、ライブなホールにも関わらず一つ一つの音がクリアで(昔、ベイシーバンドはホールでは音をぶつ切れに演奏して、聞いている人に良く聞こえるように演奏するんだ、ということを聞いたことがあります)また、一つ一つの音を注意深く大切に演奏して、全く感動しました。
 香港のSIK HAK Band 香港のSIK HAK Band
香港には在留日本人を中心にSIK HAKと云うジャズ集団があります。デキシー、コンボ、ビッグバンドなど多彩な集まりがあります。わがNFCの元メンバーが現在、活躍している縁もありまして、1997年11月、香港でジョイントし、大変、歓迎を受けました。しかし、日本とアジア経済の失速のお陰で日本人、一説には、2500世帯、約1万人が帰国してしまって、メンバー不足に陥っているようです。もし、香港へ駐在することになりましたら、訪ねてみて下さい。結構、うまいですよ。
|